【初心者】100mを速く走るための短距離走の基本!!知ってるだけで速くなる!?
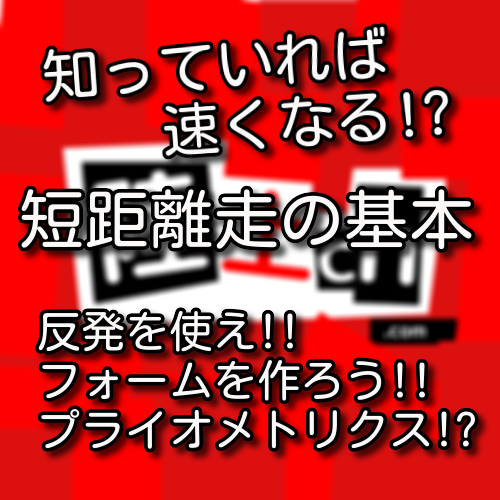
陸上は競技なので大会で結果を残すことが一番の目標にはなるものの、【大会で勝つ】だけが陸上の楽しみではありません。
陸上の大会で結果を出せるの人はほんの一握りで、そのほとんどは幼少期から俊足で学校レベルだと無双してきたような人達です。陸上部員のほとんどが大会での優勝はおろか入賞すらも経験することなく、そればかりか予選通過すら経験することなく引退していくのです…
だって、中学生・高校生の陸上競技人口は30万人もいるんですから!
とはいえ、どうせ陸上部に入るなら、大会で勝てなくても『元陸上部』として人に自慢できるくらいの走力は獲得したいもの。
ってことで今回は
経験者なら知っておきたい『速く走る』ための短距離の基本!!
をテーマにご紹介。
知っているだけで速く走れる知識や、これができるかどうかが素人と経験者の違いと言えるような、短距離走の基本的な動きについてご紹介します。
部活に入りたての初心者から、大人になって陸上を始めてみようと思っている人まで、今回紹介する内容を知って実践すれば、たちまち経験者っぽい立ち居振る舞いができるようになるでしょう!!
短距離走を速く走るための基本
陸上は才能のスポーツと言われますが、野球だってサッカーだってプロになるような人は幼少期から天才と呼ばれています。
『速く走る』ことに特化した競技である陸上では、『どうすれば速く走れるのか?』を知っているかどうかが重要。天才と言われる人は体がそれを知っているんです。じゃあ、そういう人には敵わないのか?っていうと、後天的でも頭を使って知識を付け、それを体現できさえすればある程度は戦えます。
ってことで、速く走るためには知識がかなり大事。知識さえあればそれなりに速く走れるようになるのです!!
ここではまず、知識として速く走るための基本を3つご紹介します。
①は速く走るために【反発】が大事
②は【反発】を受け止めるのが大事
③は【反発】をうまく使うのが大事
っていう話です。
①ゴムボールのように【反発】を使えば速く走れる!!
『反発を使う』これが速く走るために最も重要なキーワード。陸上は一にも二にも反発です。
速く走りたければとにかく「反発」が大事で、反発がわからなければ速く走ることはできませんし、反発さえわかっていれば普通の人より速く走れます。
特に陸上では地面がゴム(タータン)のため反発を生みやすく、この反発をどれだけうまく使えるかが記録の良し悪しに直結しています。そのため、練習ではたくさん走ることよりもフォーム作りが重要視されます。『量よりも質』で効率的に反発をもらえるフォームを身に付けるのが陸上の練習の本質です。
反発って言われても…て感じかもしれませんが、イメージとしてよく言われるのはゴムボールがバウンドするように走る!!っていうやつ。
ボールって良く弾むボールト全然弾まないボールがありますよね。速く走りたいなら、自分が良く弾むボールになったつもりでバウンドするイメージで走るんです。さらにレベルアップしたいなら、ゴムボールにスピンをかけましょう。
野球・サッカーなどの土のスポーツは反発が少ない?
陸上では高校生でも毎年200人くらいが10秒台で走っています。野球やサッカーでも俊足は大勢いますが10秒台で走れる選手となるとほとんどいません。
野球・サッカー選手の方が運動能力的には高くても、『走る』ことに限れば陸上選手に分があります。つまり、陸上と他のスポーツとでは何かが決定的に違うんです。この違いこそが、【反発】を使えるかどうかの差と言えます。
で、その差がなぜ生まれるかっていうと、地面の違いが大きい。陸上は『タータン』で野球・サッカーは『土』ですよね。
土はタータンに比べると反発が少ないため、野球やサッカーでは反発を使うことはそれほど重要ではなく、特に加速局面ではスリップが大きくて反発を十分に受けられないため、比較的筋力を使う走りが主流です。そのため、野球やサッカーの走り方そのままではどうしても10秒台レベルに達するのは難しいのです。
もし、野球選手やサッカー選手が陸上的な走りを身に付ければ10秒台が出る選手もけっこういるでしょう。
②手と足を連動させると速く走れる!!
反発が大事ですが、どうやったら反発がもらえるの?っていうのが2つめ。
手足をうまく連動させることで弾むことができる!!
簡単にいえば、良いフォームで走れってこと。
速い人と遅い人って、あきらかに手足の動かし方が違いますよね?速く走りたいなら細かいことを気にする以前に手足を連動させて動かすことが大事です。人って歩く時にも走る時にも手と足は勝手に連動して動きます。しかし、速く走ろうとするなぜか手足がバラバラになっちゃう!
手だけを頑張って振ってしまったり、足ばかりを意識して手が全く振れていなかったりということが頻発します。いわゆる力みってやつで、これを治すだけで人より速く走れる可能性が高い。
で、なぜ手足をうまく連動させたほうがいいのかっていうと、これもまた【反発】につながるのです。
手と足がぴったり連動すると、地面からの反発をロスなく使うことができるようになってパワフルな動きになります。同じ力を発揮していても、手足を連動させることで反発が使えると飛躍的に速く走れます。
腕振りが大事といわれますが、腕を振ることが大事なわけではなく、腕を振ることで反発をうまく使うことが大事なのです。これができれば速く走れる!!
『軸』も大事だよ
陸上では『軸』ってのも超重要です。
超簡単に言えば、まっすぐ立つこと。地面からの反発をクッションすることなく体で受け止めるためには膝や腰を曲げずに真っすぐに立って、まっすぐに走ることが大事。また、加速局面では軸を前傾させることでよりスムーズに加速できます。
が、軸なんて意識するのにはそれなりの経験が必要で、初心者には難しすぎます。まずは、軸よりも先に手足を連動させてちゃんと動かすことを優先しましょう。手足の連動ができれば、おそらく軸も勝手にできるはず。
③力の向きをコントロールすれば速く走れる!!
基本の3つめは
反発力を推進力方向に使え!!これです。
短距離走は前だけに向かって走る競技です。そのため、力を全て前向きに使うことができれば速く走れます。とはいえこれが非常に難しい。
遅い人って、ぴょこぴょこ跳ねてしまったり、腕を横に振ってしまったり、なんだか横向きや上向きのロスが大きくないですか?
一方、速い人ってスムーズにスーーーっと進みますよね。
技術として力をうまく扱えるようになるには練習が必要ですが、上にポンポン跳ねてしまったり、腕がブンブン横に向かってしまっている人は『力を前向きに使う』というイメージをもつだけでも飛躍的に足が速くなります。
ちなみにこの『力』っていうのは【反発力】のことです。反発を感じてそれをうまくコントロールできるようになれば間違いなく速く走れます。地面から受けた反発力を推進力にうまく変換する。これが短距離走です。
速く走るためのフォームの基本
もも上げはやっぱり大事!!
初心者のうちはいろいろと考えるとうまく走れなくなってしまいがちですが、もも上げだけをしっかり意識するだけでそれなりのフォームができます。もも上げは短距離の基本の最も初歩的な部分であり、どこまでいっても重要なポイントです。
基本として押さえるべきポイントは『見た目のフォームをキッチリ完成させる』ことです。
外から見て良い動きが出来るようになることが速く走るための最初の一歩と言えます。なかでも『もも上げ』は昔から速く走るための基本として教科書にも載っています。その発生には諸説ありますが、スプリンターの動きを分析したらももが高く上がっている選手の方がタイムが良いとうデータがあるらしいです。
突き詰めると『ももを上げないイメージ』で走るという理論もあります。しかしこれは動かし方の話で、実際の動きではももが高く上がった方が速く走れます。レベルが上がったらもも上げについてもいろいろ考えることになりますが、まずはしっかり見た目の動き(実際にももが上がるようにする)が大事です。
足を畳んで前に持ってこよう
走るという動きは連続動作のため、地面を蹴った足は早く前に持ってくる必要があります。
この『前に持ってくる』というイメージがある時点ですでに速く走れると思います。普通は速く走ろうとすると地面を強く蹴ることを意識すると思いますので、蹴った後の足の動きを意識しているということはすでに次のレベルにいます。
強く地面を蹴ることも大事ですが、蹴った足を早く前に持ってくることのほうが実は重要なのです。
後ろに蹴りだした足は伸ばしたままだとゆっくりとしか動かせませんので、膝を畳んで前に持って来るようにしましょう。よく言われているのは『かかとをお尻に付ける』イメージ。そうすれば勝手に足が畳まれるので素早く前に持ってくることができます。
もしかするとこれだけで0.5秒くらいタイムがあがるかも!?
接地は拇指球!!
速く走るためには足を着く場所も非常に大事。足を体より前に着いてしてしまう人はかかとで接地していて、これでは大きなブレーキがかかります。
そこでポイントになるのが『拇指球で接地する』というもの。いわゆるフォアフットです。
接地位置の理想は体の真下といわれていて、前過ぎるとブレーキがかかり後ろすぎると足の回転が落ちてしまいます。体の真下に接地することでブレーキのロスがなく反発がもらえ、足の回転も最大化できるのです。
で、体の真下に接地する為のイメージが拇指球で接地するというもの。コツみたいなもので、拇指球で接地すると勝手に体のほぼ真下で接地することができるのです。つまり、理想のフォームで接地すると自然と母指球で接地するフォアフットになります。
フラット接地を意識しても見た目の動きではフォアになります。
『接地の感覚』は陸上を突き詰めていっても正解がわからない非常に難しいものなのですが、10秒台を目指すくらいのレベルまでなら拇指球で接地しておけば接地位置が体の真下になって速く走れます。
っていうか、拇指球で走らないと速く走れません。
素人と陸上経験者の違いはどこ?
素人の走りと陸上の走りは大きく違います。詳しいことがわかっていなくても陸上でそれなりに経験を積んでいるとそれっぽい走りに収束していきます。
この差ってなんなんでしょう?
素人走りと陸上走りの違いがわかっていれば、陸上っぽい動きを簡単に身に付けることができるかも!?
反発を使った走りか?力を使った走りか?
一番大きな違いはやはり『反発の概念』があるかどうかです。
管理人も中学までサッカーをやっていてかなり俊足な部類でしたが、一度も反発について考えたことはありませんでした。で、陸上部に入って反発を知り、反発を意識したらそれだけでタイムが上がりました。
普通に生活していて地面からの反発を感じることはまずありませんが、陸上では非常に重要な要素である反発。反発というものがあるということを知っているかどうかの差。この差が素人と陸上経験者の最大の違いと言えましょう。
見た目には同じ動きに見えても、頭の先まで反発を伝えている場合とそうでない場合には体が受け止める反発力は雲泥の差が生まれます。そしてタイムにも大きな違いが生まれます。
感覚の動きと実際の動きの違いがわかっているか?
陸上は才能のスポーツと言われるのは感覚が大きなウェイトを占めるからです。
できる人はなんとなくできているものが、できない人にはなにをやってもできない。これが言い換えれば才能なのです。で、この感覚を後から習得できると陸上的な走りができるようになります。
同じ高さまで膝や腕が上がっていてもなんとなく硬く見えたりパワフルに見えたりといった違いが出ますが、この差はまさに感覚の差です。力を入れていないのにスムーズで力強い動きができるのが経験者で、力んでいて伸びがない動きなのが素人。
で、これを解消するには『感覚の動きと実際の動きは違う』ということが分かればいいんです。まあ、難しいんですが。
簡単に言えば、『膝を高く上げたいなら膝を高く上げるイメージではなく、腕を大きく振るイメージが必要』っていう感じ。
他の表現をいくつか挙げると..
足を速くスイングするには蹴った足をすぐに足を前に持ってくるイメージ
スタートで前傾するには地面を最後までしっかり押し切るイメージ
足首を固定するにはフラットに接地するイメージ
などなど。
で、これができれば足が流れずに走れたり、体が反らずに真っすぐに走れたりします。
足を鞭のように使っているか?(末端操作)
陸上では末端操作はダメとされています。末端っていうのは手や足のことで、対して中心っていうのはいわゆる体幹や骨盤のことです。陸上では体の中心に近い部分を動かすことで、それにつられて末端が動くというのが理想の動きとされているのです。
上で説明した『もも上げ』についても、見た目の動きでは『ももを高く上げる』なのですが、実際に動かしている人のイメージでは『ももが上がっている時には既に足を下げている』という風になっているのです。意識と動きにはタイムラグがあるんです。
難しい…
鞭(ムチ)をイメージするとわかりやすいのですが、先っぽが高く上がっていても手もとはすでに振り下げているはずです。
この鞭のイメージで手足を動かすことができているかどうかが陸上の動きです。
プライオメトリクスって知ってる?
短距離走はいわゆる瞬発系です。短い時間で強い力を出せるかどうかが足の速さにつながります。で、瞬発系にも2種類あって、ベンチプレスのようにグーっと力を加えてパワーを出すものと、陸上や野球のように一瞬で力を伝えるものがあるのです。
この違いは『筋肉の力を使うか腱の力を使うか』の違いです。
腱を使う種目はプライオメトリクスと呼ばれていて、プライオメトリクス系の種目では腱を使えるかどうかが決定的な記録の差になります。
プライオメトリクス系ではごく一瞬の接地時間で強い力を発揮します。逆に、接地時間が長くなってしまうと力が分散してしまうのです。この力の使い方の違いが分かっていないと速く走れません。
いわゆる無駄な筋肉なんていうのはこの違いのことです。陸上では当然筋肉は必要ですが、陸上の接地は筋肉が十分な力を発揮できるほど長くないのです。
筋肉っていうのは、まず腱が伸びてそれにつられて筋肉も伸びます。で、反射っていのはまず腱で起こります。この一瞬が陸上の接地。ゴムボールのように弾んで走るなんていう表現もされます。
陸上は筋肉ではなく腱を使って走る!!
これができるかどうかが素人と陸上経験者の力の出し方の根本的な違いです。


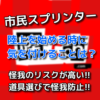
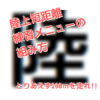

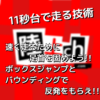
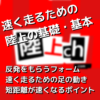

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません